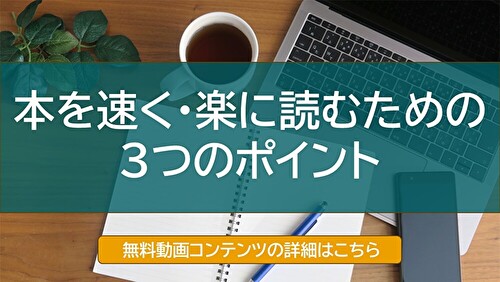なぜ「かたまり読み」が速読のカギなのか?
私たちはふだん、本や文章を読むとき、一文字一文字を丁寧に追うように視線を動かしています。これは、小学校で音読を学んだ時からの習慣とも言えるでしょう。しかし、この“一文字ずつ読み”では、視線の動きが細かくなりすぎてしまい、読書スピードが制限される原因になります。
速読の世界では、視線をより大きく、よりリズミカルに動かし、「意味のかたまり(チャンク)」を一度に捉えることが重要とされています。これは単なるテクニックではなく、脳の認知処理に基づいた合理的な方法です。
認知心理学では、人間が一度に認識・処理できる情報量には限界があり、それを効率的にまとめることで理解や記憶のスピードが上がるとされています。この「チャンク処理」は、速読においても同様で、「単語や短いフレーズ」を一つの単位として捉えることで、読み取り効率が飛躍的に高まるのです。
「かたまりで読む」とは具体的にどういうこと?
では、「かたまりで読む」とは、具体的にどのような読み方なのでしょうか?実は文章を読むときは、誰でもある程度の「かたまり」で読んでいます。絶対に複数の文字が目に入ってっくるので「一文字一文字読む」ということはできず、だいたい2文字~5文字程度のかたまりで読んでいるのです。
たとえば、以下の文章を読んでみてください。
「速読の基本は、一文字ずつ読むのではなく、単語や短いフレーズ単位で視線を動かすことです。」
この文章を読むときには、恐らく意識はしていないと思いますが、次のような感じでかたまりで捉えています。
- 速読の | 基本は、 | 一文字ずつ | 読むのではなく、 | 単語や | 短いフレーズ | 単位で |視線を |動かす | ことです。
速読の実践でいう「かたまりで読む」というのは、このかたまりを大きくする、ということです。同じ文章を次のような感じで読んでいきます。
- 速読の基本は、 | 一文字ずつ読むのではなく、 | 単語や短いフレーズ単位で | 視線を動かすことです。
つまり、1行の中にある意味のまとまり(フレーズ)を「ひとまとまり」として視線を移動させるのです。
例えば、歩くときに歩幅が小さい人よりも歩幅が大きい人の方が、歩くスピードは速くなるのと同じ理屈です。
このとき、文章全体の意味を100%理解しようとするのではなく、まずは視線をテンポよく動かすことに意識を向けます。
ステップ別トレーニング方法
まずは、自分の「読み癖」を把握することから始めましょう。
- 短めの文章を黙読してみる。
- 視線がどのように動いているかを意識する。
- 一文字ずつ追っている感覚があれば、それをしっかりと「気づく」。
この「気づき」こそが、次のステップへの第一歩になります。
今度は、意味を理解しなくてよいので、視線を“トン・トン・トン”とリズムよく動かす練習をしてみましょう。
- 1行の文章を目でざっと見渡し、等間隔で2〜3か所に分ける。
- 読まずに「視る」感覚で、視線だけをパッパッパッと動かす。
これは、筋トレのようなトレーニングで、視線の動きを柔軟にし、「一文字ずつ読む」クセから脱却する効果があります。
視線の動かし方に慣れてきたら、次は「意味のかたまり」に意識を向けましょう。
- 句読点で文章を分けてみる。
- 助詞や助動詞の位置を目安に、フレーズごとに線を引いてみる。
- 1ブロック=1視線というイメージで黙読する。
例: 本を読んでいて、 | つい同じ箇所を | 何度も読んでしまう。
このように、自然な言葉の切れ目を見つけて読むことで、意味理解とスピードが両立しやすくなります。
最後は実践練習です。手持ちの本を開いて、1行を2〜3分割して読み進めてみましょう。
最初は少し読みづらく感じるかもしれませんが、続けるうちに視線の動きにリズムが出てきて、理解にもスピードにも余裕が生まれてきます。
よくあるつまずきポイントと対処法
「意味が頭に入らない」と感じる
→ 最初は「視線の動き」に集中してOK。理解は後から追いついてきます。
「視線が戻ってしまう」
→ 読み飛ばしやすい単語が出てくると、つい戻ってしまうのは自然な反応。最初は「戻らずに読み切る」ことにチャレンジしましょう。
「かたまりが分からない」
→ 句読点、助詞、接続詞がある場所を基準にして区切ることで、感覚がつかめてきます。
かたまり読みができると何が変わるか?
- 読書スピードが格段に上がる
- 視線のムダな移動が減るため、疲労感が軽減される
- 理解しながら読むことができ、読み直しが減る
- 集中力が持続しやすくなる
さらにこの「かたまり読み」のスキルは、次に紹介する「視野を広げるトレーニング」と非常に相性が良いのです。
速く・楽に読めるようになる3つのポイント、実演で体感してみませんか?
「一文字ずつ読むクセをやめ、かたまりで読む」ことで読書のスピードと理解力が上がるーーその感覚をつかみかけている今こそ、次のステップへ進むタイミングです。
文字をかたまりで捉えることに加え、視野を広げてかたまりを大きく捉えること、そして視点の移動スピードを速くすること。この3つが組み合わさることで、無理なく自然に“速く読める”読書が可能になります。
そんな速読の基本「3つのポイント」を、動画でわかりやすく実演しながら解説した【無料コンテンツ】をご用意しました。
さらに、3つのポイントを自分でトレーニングできる「実践ワークPDF」もプレゼントしています。まずはこの無料オファーで、「速く・楽に読む感覚」を体験してみてください。
次に取り組むべきトレーニング
「かたまり読み」は、視線の動きを意識的に変えるための基礎トレーニングです。しかし、速読のスピードをさらに高め、安定した読み方を身につけるには、「視野の広さ」を鍛えることが欠かせません。
視野が狭いままだと、せっかくかたまりで読もうとしても、視界に入る情報量が限られてしまうため、スムーズに読み進めることができません。
そこで次は、「視野を広げるトレーニング」に進みましょう。
視野拡大によって、1回の視線移動でとらえられる文字数が増え、「かたまり読み」の効果がさらに発揮されるようになります。
👉【次のステップへ】視野を広げるトレーニングに進む
よくあるご質問(FAQ)
A:「かたまりで読む」とは、文章を単語や短いフレーズ単位で視線に収めて読む方法です。
一文字ずつ読むのではなく、意味のまとまりごとに視線を動かすことで、読書スピードと理解力の両立を目指します。視線の無駄な移動が減り、疲労感の軽減にもつながります。
A:まずは自分が一文字ずつ読んでいることに“気づく”ことが大切です。
その後、文章を1行につき2〜3分割し、意味を追わず視線だけをリズムよく動かす練習をしましょう。慣れてきたら「意味のかたまり」を意識して黙読することで、自然とクセが改善されていきます。
A:視線の「歩幅」が大きくなるからです。
一文字ずつ読む場合と比べて、視線の移動回数が少なくなり、処理速度が上がるため、結果として読むスピードも向上します。歩幅が大きい人が速く歩けるのと同じイメージです。
著者プロフィール

渡辺篤志:「株式会社いろどり」代表 「速読研究会」主宰
100冊以上の速読術・読書術・勉強法を学び、「これなら誰にでも習得できる」という独自のトレーニングメソッドを作り上げ、10年以上に渡り2000名以上に指導。著書に「身につく速読、身につかない速読 ~1冊1時間を目指す、挫折知らずの現実的速読トレーニング~」がある。