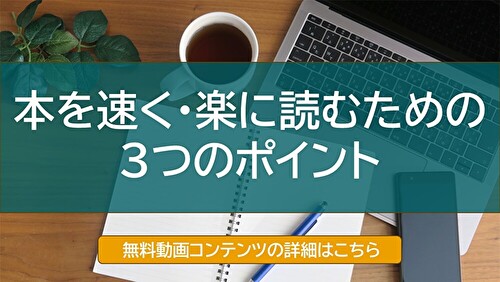なぜ文章構造をつかむ必要があるのか?
文章を速く読めるようになっても、それだけでは意味がありません。本当に大切なのは、「何が言いたいのか?」をきちんとキャッチできること。
そして、それを可能にするのが「構造理解の力」です。
構造をつかめるようになると、読みながら頭の中に“地図”が描かれていきます。「今は導入部分だな」「これは具体例だ」「この段落がまとめだな」といった具合に、情報の流れが整理されていくのです。
これは、単なる読書スキルではありません。報告書、企画書、プレゼン資料―あらゆるビジネスシーンにおいて、「構造を読む力」はそのまま「構造をつくる力」にもつながっていきます。
STEP1:段落ごとの「骨組み」を把握しよう
まず、文章の構成単位である「段落」に目を向けてみましょう。段落とは、一つの話題・主張を中心に構成された“まとまり”です。ここを適当に読んでしまうと、内容の輪郭がぼやけたまま進んでしまいます。
主題文を見つける
多くの場合、段落の最初か最後に「その段落で一番言いたいこと」が書かれています。たとえば─
「成功する習慣を身につけるには、まず“続けられる環境”を整えることが大切だ。」
この1文があれば、その段落では「環境づくりの重要性」が展開されると予想できますよね。
接続詞を手がかりに流れをつかむ
「しかし」「つまり」「たとえば」「その結果」などの接続語は、話の展開を読み解くヒントになります。接続詞をマーカーで塗ってみるだけでも、文章の“骨組み”が見えてきます。
接続詞だけでなく、「ゆえに」「大事なのは」「重要なのは」「このグラフから言えることは」「このことから分かるように」などのような言葉は、このすぐ後に重要な文章が来る「シグナルワード」ですので、見落とさないようにしましょう。
指示語を追いかける
「これ」「それ」「このような」などの指示語は、「何を指しているか?」を意識して読むことで、文と文の関係がつかめます。指示語を放っておくと、話が急に飛んだように感じられるので注意。
段落ごとの要点に意識を向けるだけでも、読みの精度はグンと上がります。
STEP2:構造を「見える化」してみる
文章を読むときに、頭の中で「地図」が描ける人は強い。どこが導入で、どこが主張で、どこに例が出てくるのか。
そして、どこでまとめに入るのか。
この“地図”があれば、途中で迷子にならずにすみますし、読んだあとも内容が記憶に残りやすくなります。そのためのトレーニングが、「構造を見える化する力」を育てることです。
まずは「構造パターン」を知っておく
構造を読み取るためには、まず文章の“設計パターン”をいくつか知っておくと便利です。よくあるパターンには、こんなものがあります:
- 三部構成(序論・本論・結論)
論文やビジネスレポートでよく見られる形式。最初に問題提起、本論で論点展開、最後にまとめ。 - 起承転結
ストーリー性のある展開。エッセイやコラム、プレゼン資料にもよく使われます。 - PREP法(結論・理由・具体例・結論)
SNSやプレゼン、簡潔に伝えるビジネスシーンで多用されます。英語で書かれた文章(翻訳も含めて)も、このパターンが多いです。
読んでいる本のタイプに応じて、「あ、これはこのパターンかな?」と当てはめながら読むと、ぐっと全体像が見えやすくなります。
でも、実際の本は“型通り”じゃないことも多い
注意しておきたいのは、特にビジネス書や自己啓発書では、「構成がゆるい」「一貫してない」と感じるケースが少なくないことです。
とくに、
- 読みやすさを重視した入門書
- 会話調で書かれた本
- コラム形式の本
こういった本では、「章によって話の構造が違う」「どこが本論かよく分からない」なんてこともよくあります。
でも、だからこそ、読者側が“型に縛られすぎず”、柔軟に構造を読み取る力が求められるんですね。
読みながら“ラベル”をつけていく
私がおすすめするのは、「頭の中で、ざっくりラベルをつけて読む」習慣です。
たとえばこんな感じ:
- 「ここは導入だな」→【導入】
- 「これは筆者の主張」→【主張】
- 「ここは例え話だ」→【例示】
- 「ここで話が展開した」→【転換】
- 「結論っぽいな」→【まとめ】
紙の本なら余白にメモしてもいいし、Kindleならマーカーやメモ機能を使ってもOK。そうやって、文章を“塊”として把握する習慣がつくと、読むスピードと理解度が一緒に上がっていきます。
構造は「図」にするともっとわかりやすい
図解が得意な人であれば、文章の流れを図にしてみるのもおすすめです。たとえば…
コピーする編集する【テーマ提示】
↓
【主張】
↓
【理由①→例①】
↓
【理由②→例②】
↓
【結論/提案】
こうして“流れ”を目に見える形で描くと、「あ、こういう順番で話してたんだな」と整理されます。これは特に、専門性の高い書籍や、論理の複雑な話を読み解くときに威力を発揮します。
ChatGPTで「構造マップ」を確認してみよう
構造を読み取る練習は、一人でやろうとするとけっこう大変です。
「ちゃんと読めてるのかな?」
「自分のまとめは合ってるのか?」
そうやって迷うこともあるでしょう。
そんなときに頼れるのが、ChatGPTという読み取り補助ツールです。ChatGPTなどのAIを利用する人もだいぶ増えたと思いますが、調べものをするだけでなく「読書のパートナー」として役立つのです。
私自身がやっている方法(初心者にもおすすめ)
初心者にもおすすめなのが、私が実際にやっているこの3ステップ:
①:章タイトル・節・小見出しをすべて書き出す
→ これだけで、本の“骨組み”が見えてきます。
②:各見出しの下に、大事だと思った本文をそのまま抜き出す
→ 要約や意訳は不要。「これ重要そう」と思った文章をそのまま書き出すだけです。もし可能なら、一端頭で覚えてから「本を見ないで」書き出すとより、記憶にも残りやすくなり効果的です。(すぐに忘れてしまいますが、一度でも頭に入れるか否かはだいぶ違います)
③:ChatGPTに貼り付けて、「この章を構造的に整理してください」と依頼
→ 論理展開、要点、結論の流れを視覚化して返してくれます。たとえば次のようなプロンプト(ChatGPTへの指示文)を使います:
「この章の構造を、段落ごとに要点をまとめて整理してください。
三部構成やPREP法に当てはまる部分があれば、教えてください。」
これだけで、自分では気づかなかった“つながり”や“抜け”がはっきりと見えてきます。
さらに一歩進んだ活用法
ChatGPTで構造を出力してもらったあと、次のような比較をすると非常に効果的です。
- 自分のまとめ vs ChatGPTの構造整理
- 自分の見出しの理解 vs AIの分析
- どの文を“主張”と判断したか?の違い
このプロセスを繰り返すだけで、「どこに着目すれば構造がつかめるのか?」という感覚がぐんぐん育っていきます。
よくあるつまずきとその対処法
ここで、よくある悩みとその対策もご紹介しておきます。
全部を丁寧に読もうとしてしまう
まじめな人ほど、「すべてを完璧に理解しよう」とします。でも、文章には“要点”と“補足”があります。まずは「何が核となる主張なのか?」を見つける意識を持ちましょう。
要点がつかめず、なんとなく流し読みになる
読書中に「これは何を言いたいんだっけ?」と感じたら、一度止まって主題文を探してください。慣れないうちは、見出しや太字、マーカーなど“視覚的ヒント”をフル活用しましょう。
「速読のトレーニング」という観点では、読み返しはしない方がいいですが、「内容を理解する」ためには、必要があればいくらでも読み返してください。
構造が複雑で、頭がこんがらがる
そんなときは、一度紙に書き出して整理するのが効果的です。図にすれば、頭の中でごちゃついていた情報が一気にクリアになります。
習慣化のコツ|毎日の読書にどう取り入れる?
読書を変えるために、特別な時間は必要ありません。1日1章(あるいは1節)だけでも「要点まとめ+構造ラベル付け」の練習を取り入れてみましょう。
おすすめは、朝の10分や通勤中など、“スキマ時間”にやること。ChatGPTをスマホで開きながら、「この段落の要点は?」と聞くのもいい習慣です。
「読む力」の土台を、今こそ整えませんか?
文章の構造を見抜けるようになると、読書の世界がぐっと広がります。けれどその前提として必要なのが、「速く・楽に読めるベースの力」。
「文字をかたまりで捉える力」、「広い視野で読む力」、「視点をスムーズに動かす力」――こうした“読みの身体感覚”が整ってこそ、構造も意味も自然に入ってくるのです。
そこで今回、速読初心者の方にもやさしい無料の動画コンテンツ「本を速く・楽に読むための3つのポイント」をご用意しました。
さらに、すぐに実践できる「3つのポイント実践ワーク」もプレゼント中。読書の土台を整えたい方は、ぜひこちらから受け取ってください。
次のステップ:「読解力を鍛えるトレーニング」へ
さて、構造が見えるようになってくると、今度は「もっと深く意味を理解したい」という気持ちが生まれてきます。
次のステップでは、
・筆者の意図
・背景にある価値観
・行間にあるメッセージ
などの“目に見えないもの”を読み取る「読解力のトレーニング」に進んでいきます。
ここまでの土台があれば、もう大丈夫。次は「読みながら考える力」を育てる段階です。一緒に進んでいきましょう。
👉【次のステップへ】「読解力「読解力を鍛えるトレーニング」へ進む
よくあるご質問(FAQ)
A:情報の全体像を素早く把握できるようになるため、読書スピードと理解度の両方が向上します。
文章構造を理解することで、「今、何を読んでいるのか」「次に何が来るのか」といった流れが“地図”のように見えるようになります。これにより、長文を読んでも迷子にならず、必要な情報を的確にキャッチできるようになります。ビジネス文書の要点把握やプレゼン資料の読み解きにも役立ちます。
A:代表的な構造には「三部構成」「起承転結」「PREP法」などがあり、内容や目的に応じて柔軟に読み方を変えるのがコツです。
論理的な文章では「序論・本論・結論」といった三部構成が多く使われますが、エッセイでは「起承転結」、SNSやビジネス文章では「結論→理由→事例→結論(PREP法)」などもよく見られます。本のジャンルや著者によって構成が異なるため、読者側が複数のパターンを知っておくと柔軟に対応できます。
A:章や節の見出しと大事な文を抜き出して貼り付け、「構造的に整理してください」と依頼するだけでOKです。
初心者には、「①章・節・小見出しを抜き出す」「②本文の重要部分をそのまま書き出す」「③ChatGPTに構造整理を依頼する」という3ステップがおすすめです。自分では気づかなかった要点や展開の論理が可視化され、読書の理解度が飛躍的に高まります。
著者プロフィール

渡辺篤志:「株式会社いろどり」代表 「速読研究会」主宰
100冊以上の速読術・読書術・勉強法を学び、「これなら誰にでも習得できる」という独自のトレーニングメソッドを作り上げ、10年以上に渡り2000名以上に指導。著書に「身につく速読、身につかない速読 ~1冊1時間を目指す、挫折知らずの現実的速読トレーニング~」がある。