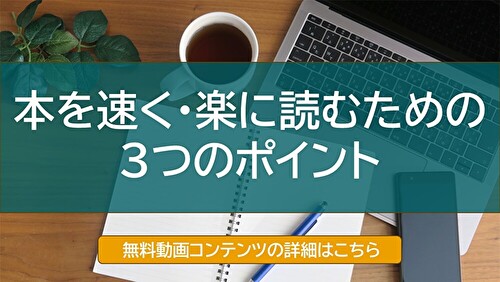読解力とは何か?速読との違いと関係
読解力とは「見えないものを読み取る力」
読解力というと、学校でのテスト対策を思い浮かべる人もいるかもしれません。でも、私たちが日常で求められる読解力とは、もっと生きたスキルです。たとえば、誰かの発言の裏にある意図を読み取る。メールの文面から感情の機微を感じ取る。そんな「行間を読む力」が、まさに読解力なのです。
速く読むだけでは足りない理由
速読だけで満足してしまうと、重要な要素が抜け落ちます。速く読めても、「なぜこの話をしているのか?」「何を伝えたいのか?」がつかめなければ、行動につながる読書にはなりません。読解力が加わることで、速読の成果は何倍にもなるのです。
読解力を高める読み方
問い・目的・立場に注目する
文章の背後には、かならず「書いた理由」があります。たとえば、「読書術の本」なら、「読者にどんな変化を与えたいのか?」を考えながら読むだけでも、視点がまるで変わってきます。
- 筆者はどんな問題意識を持っている?
- どんな行動を読者に促したい?
- どんな前提を共有している?
こうした「問い」を持って読むことが、読解の入口になります。
ChatGPTで意図を要約するプロンプト例
読書中に「筆者の意図がよくわからない」と感じたら、ChatGPTの出番です。たとえば以下のように入力してみましょう。
“この文章を読んで、筆者が一番伝えたいことを1~2文で要約してください。
どんな問題意識が背景にあるかも教えてください”これにより、自分の読みとAIの読みを比較し、観察力を育てることができます。
文章の前提をどう読み取るか
文章には、「書かれていない前提」がたくさん含まれています。たとえば、
- 資本主義は当然の前提として話が進んでいる
- 読書が重要という価値観が共有されている
こうした前提に気づけるかどうかで、文章の読み方は大きく変わります。読書中に「あれ、なんでそう言い切れるんだろう?」と感じたとき、それは前提に気づくチャンスです。
ChatGPTで筆者の立場や背景を分析する
“この著者が前提としている価値観や立場を教えてください。
読者に何を当然と考えているか、暗黙の了解があれば示してください”こうしたプロンプトを使えば、自分だけでは気づけなかった「視点の偏り」や「文化的背景」にもアクセスできます。
比喩・皮肉・暗示を読み取るコツ
行間とは、「書かれていないけど伝わること」。たとえば、
- 皮肉:「それは素晴らしいご提案ですね(棒読み)」
- 比喩:「この制度はまるで穴の開いたバケツのようだ」
こういった表現を、文字どおりに受け取ってしまうと、筆者の真意が見えなくなります。「この表現にはどんな感情がこもっているか?」という視点を持つだけで、文章の奥行きがぐっと増します。
ChatGPTで含意を探る活用例
“この一文には、どんな含意や暗示があると考えられますか?
表現に込められた筆者の感情を推測してください”読書に慣れていないうちは、AIとの「読解ディスカッション」が大きな助けになります。
読解につまずく原因と対処法
全部理解しようとする完璧主義
読書初心者に多いのが、「全部を理解しないといけない」という思い込み。でも、実際の読書では「何を読み取ったか」が大切です。まずは筆者の主張や意図、気になった表現などを拾うだけでOKです。
感情移入しすぎて筆者の意図を見失う
共感することは大事ですが、感情に引っ張られすぎると、筆者の本当の意図が見えなくなることもあります。一歩引いて、客観的な読みも心がけましょう。
習慣化のコツ|『意図・前提・行間』を記録に残す
3ステップ読書ジャーナルのすすめ
読書のあと、次の3つを書き出すだけで読解力は確実に上がります。
- 筆者の意図(なぜこの本を書いたか?)
- 前提(どんな価値観が前提になっているか?)
- 行間(含意・裏メッセージ・比喩など)
この3点を意識しながら読み、記録する習慣をつけましょう。
ChatGPTで読後対話をする方法
読み終えたら、次のようにChatGPTと対話してみてください。
“この本の核心はどこにあったと思いますか?
私はこう感じたけど、別の視点はありますか?”AIとの「読みの照らし合わせ」は、自己理解と客観的視点をバランスよく育ててくれます。
読解力を育てるために、今すぐ始められる“具体的な一歩”とは?
読解力を高めたい──そう思っても、「読むのが遅い」「内容が頭に入らない」と感じていませんか?
その原因は、「意味を読む力」だけでなく、そもそも文字のとらえ方や視点の動かし方にあるかもしれません。
そこでご案内するのが、無料で受け取れる動画コンテンツ「本を速く・楽に読むための3つのポイント」です。
- 文字をかたまりで捉える
- 視野を広げてかたまりを大きくする
- 視点の移動を速くする
この3つをわかりやすく実演し、実践ワークでトレーニングできる特典もご用意しています。「深く読む力」を育てたいあなたにこそ、まずは「速く・楽に読む基礎力」から整えてみませんか?
次のステップ:『普段の読書術』へ
ここまでで、速く読む力・構造をつかむ力・意味を読む力の3つがそろいました。
次はいよいよ、これらを統合して「好きな本を読みながら自然と速読力が育つ日常読書術」に進みます。構えて読むのではなく、楽しみながら深く読む。そんな“ふだんの読書”こそが、最も効果的なトレーニングになります。
👉【次のステップへ】「好きな本を読むだけで読むスピードが自然に速くなる、『普段の読書術』」へ進む
よくあるご質問(FAQ)
A: 読解力を育てるには、読むたびに「筆者の意図」「背景の前提」「行間の含意」の3点に注目するのが効果的です。
特に、読後にそれらを一言で書き出す「3ステップ読書ジャーナル」は、記憶への定着と気づきの深まりを促します。
- 【意図】なぜこの文章が書かれたのか?
- 【前提】どんな価値観が背景にあるのか?
- 【行間】直接書かれていない、比喩や含意は何か?
読書のたびにこのフレームで振り返ることで、思考が深まり、行動につながる読書ができるようになります。
A.:読んだ後にChatGPTと「対話」するのがおすすめです。
たとえば次のようなプロンプトが効果的です:
- 「この章の筆者の意図を1文で要約してください」
- 「どんな価値観が前提になっていますか?」
- 「この一文に込められた感情や比喩を分析してください」
AIと読み比べをすることで、自分の読解のクセや視点の違いに気づけ、学びが一層深まります
A: 読解力とは、文章に込められた筆者の意図や価値観、行間の意味を読み取る力のことです。
一方、速読は「読むスピード」に注目したスキル。両者は対立するものではなく、速読で構造をつかみ、読解力で深く意味をとらえることで、実践的な読書力が育ちます。
著者プロフィール

渡辺篤志:「株式会社いろどり」代表 「速読研究会」主宰
100冊以上の速読術・読書術・勉強法を学び、「これなら誰にでも習得できる」という独自のトレーニングメソッドを作り上げ、10年以上に渡り2000名以上に指導。著書に「身につく速読、身につかない速読 ~1冊1時間を目指す、挫折知らずの現実的速読トレーニング~」がある。