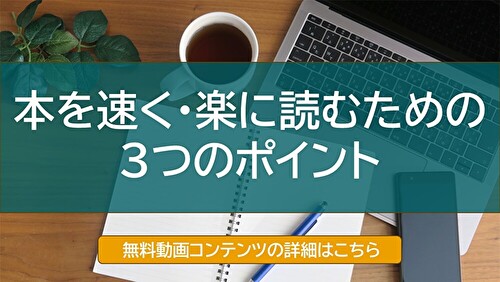速読が「理解を犠牲にしない読み方」である理由
多くの人が、「速読」と聞いてまず思い浮かべるのは、“一瞬でページをめくり、内容が頭に入ってくる”というイメージでしょう。
しかしそれは、一部の特化した訓練者による特殊な技術であり、この記事で扱うのは理解を前提とした現実的な速読法です。
速読の仕組みは、次の3つのシステムを調整・強化することで成り立っています:
- 視覚処理の最適化(目の使い方)
- 脳内処理のテンポアップ(認知の速度)
- 集中状態の誘発と持続(注意力)
これらはそれぞれ独立しているようでいて、密接に連動しています。速読とは、「速さ」ではなく「読書行動全体のリズム調整」と考えると、非常に理解しやすくなります。
視覚処理の最適化~「見る力」が速さの土台になる
目は意外とムダな動きをしている
私たちの目は、1文字ずつ見ているるわけではありません。実際には、数文字〜数単語を「かたまり」で捉えながら、視点(視線)が“跳ぶように”動いています。これをサッケード運動(saccade)と呼びます。初心者が本を読むとき、無意識にこの「視点の動き」が細かすぎて遅くなっていることがよくあります。
速読の第一歩は、この「文字のかたまりで捉えていることを意識し、そのかたまりを大きくする」ことなのです。例えば、歩幅が小さい人よりも歩幅が大きい人の方が、速く歩くことができるのと同じ理屈です。
「文字のかたまりを大きくする」とは、どういうことか?
直前の文章「例えば、歩幅が小さい人よりも歩幅が大きい人の方が、速く歩くことができるのと同じ理屈です。」を例にして考えてみましょう。
かたまりが小さい読み方というのは、次のような読み方です。
例えば、 | 歩幅が | 小さい | 人よりも | 歩幅が | 大きい | 人の方が、 | 速く歩く | ことが | できるのと | 同じ理屈です。
かたまりを大きくして読むというのは、次のような感覚です。
例えば、 | 歩幅が小さい人よりも | 歩幅が大きい人の方が、 | 速く歩くことができるのと | 同じ理屈です。
文字のかたまりの大きさ=歩幅の違いがイメージできるのではないでしょうか。
視野を「広げる」ことは可能か?
訓練によって周辺視野を鍛えることは可能です。たとえば、今この文章をパソコンで読まれているかスマホで読まれているか分かりませんが、1行の中央に視線を置いたまま、行の左右を意識するような視野拡大トレーニングを行うと、ページ全体を俯瞰する力がつきます。
縦書きの本の場合も同様に、1行の中央に視線を置いたまま、行の上下を意識するようなトレーニングをすることで、視野は広がっていきます。
認知処理スピードの調整~「内音声化のスピード」を上げる
速読に関する多くの本やウェブサイトでは、必ずといっていいほど、次のようなアドバイスが書かれています。
「本を読むときに、頭の中で音読しないようにしましょう」
「文字を読むときに“声”が聞こえる癖があると、速読はできません」
こうした言葉を見て、「音を思い浮かべてしまう自分は、速読に向いていないのでは…?」と感じた人も多いのではないでしょうか。
しかし、ここにこそ大きな落とし穴があります。この「音を浮かべないようにしよう」という意識こそが、実は速読を難しくしてしまうのです。
“内音声化”は自然な働きである
私たちは小さいころから、文字を読む=音声化する行為として学んできました。それは、声に出す「音読」だけでなく、頭の中で声を浮かべる「黙読(内音声化)」も含まれます。
つまり、文章を読むときに頭の中で声が聞こえるのは、極めて自然な脳の働きなのです。
この「内音声化」を無理に抑えようとすると、かえって文字がうまく認識できなくなり、理解度が極端に落ちるという現象が起こります。特に初心者ほどこのギャップに苦しみ、「速読ってやっぱり無理かも…」と挫折してしまう原因になります。
大切なのは「音をなくす」ではなく「音のスピードを上げる」こと
ではどうすればいいか?
答えはシンプルです。
「内音声化をやめる」のではなく、
「内音声化のスピードを上げる」ことを意識してください。
たとえば、普段1行を5秒かけて読んでいるとしたら、同じ内容を3秒、2秒で読むようにテンポアップしていく。それだけで、音は聞こえたままでも、読むスピードは確実に上がっていきます。
このように“無理のない速さ”でテンポを上げていくことこそが、現実的な速読の第一歩なのです。
スピードの目安は「2〜3倍」まで
もちろん、内音声化のスピードには限界があります。脳の情報処理スピードには個人差がありますが、実用的な速読では、通常の読書スピードの2〜3倍程度が現実的な上限とされています。
たとえば、平均的な社会人の読書スピードは1分間に400〜600文字程度ですが、これが1000文字~2000文字程度になれば、十分に「速読レベル」といえる範囲です。
それ以上のスピードを目指そうと思った時に、はじめて「内音声化を抑える」必要が出てくるのですが、そこまで速くする必要が本当にあるのか?を一度考える必要があると思います。
特殊なトレーニングをしてスピードを速くするよりも、本の構造を理解して要点をつかみ、読解力を身に付ける練習などをすることの方が、はるかに実用的で現実的ではないでしょうか
集中力と脳のテンポの一致|速く読むほど集中できる理由
ゆっくり読むほど、実は「頭に入らない」
これは意外に思われるかもしれませんが、遅いスピードで読んでいる方が、集中力が途切れやすいという現象が起こります。なぜなら、脳は「一定のテンポで処理される刺激」に反応しやすく、テンポが遅すぎると退屈してしまうからです。
集中モードに入る“速さのゾーン”がある
たとえば、ランニングにおける「一定のペースで走ったほうが気持ちいい」といった感覚。読書もそれに近く、自分に合ったリズム(没入テンポ)に乗ると、理解力と集中力が同時に高まります。
この状態に入ると、読書中の時間感覚がなくなり、「気づけば本を半分読み終えていた」といった体験にもつながります。
「速く読むと集中力が育つ」という逆説
読書は集中力がないとできない。でも、速く読むことで集中力が鍛えられる。これは速読における最大の“逆説的効果”です。
速読に取り組むことで、短時間に多くの情報を処理しようとする「能動的な読み方」に変化します。すると、読み手の意識が自然と引き締まり、雑念が入りにくくなります。
結果として、集中力そのものが強化されるという現象が起こるのです。
書籍の構造理解|「読む前の準備」が読みやすさを決める
本の「地図」を先に手に入れよう
初めての場所に行くとき、地図やナビがあれば早くたどり着けます。本も同様で、構成や目的を先に把握しておくことで、理解しながらスピーディに読み進められるようになります。
チェックすべき項目:
- 目次(全体構造)
- まえがき、あとがき(著者の意図)
- 各章の見出し(主張の配置)
- 太字・図解・まとめ(キーメッセージ)
これらを読みながら「この本はどんな問いに答えてくれるのか?」を自分なりに定義するだけで、読み進めやすさが格段にアップします。
まとめ|速読の仕組みは、「読む力」の総合強化だった
速読の仕組みとは、一言でいえば「読む行動の効率化」。
単に速く読むことではなく、
- 目の使い方(視野・視点移動)
- 脳の処理リズム(黙読スピード)
- 集中力の引き出し方
- 本の構造把握力
といった複数の要素を組み合わせていく、総合的な“読書スキルの再設計”です。
しかも、この技術は一部の特別な人だけのものではなく、誰もが段階的にトレーニングできるもの。「ゆっくり丁寧に読まないと理解できない」という思い込みを手放すところから、速読の学びは始まります。
理解しながら速く読むための“最初の一歩”を手に入れませんか?
ここまで読んで、「速読は特別な才能ではなく、誰でも段階的に身につけられる技術だ」ということを感じていただけたと思います。では、実際に今日から始められる第一歩は何でしょうか?
それが、「文字をかたまりで捉える」「視野を広げてかたまりを大きくする」「視点の移動スピードを上げる」という3つのポイントです。
この3つは、速読の土台となる“見る力”を育て、理解度を保ったまま読むスピードを高めるための最重要スキルです。無料でお届けする動画コンテンツでは、この3つのポイントを実演付きでわかりやすく解説し、さらに日常で使えるトレーニング方法をまとめた実践ワークもセットでお渡しします。
あなたも、読むスピードと理解力を同時に伸ばす一歩を踏み出してみませんか?
次は「速読で得られる具体的なメリット」を知ろう
速読が「仕組みとして成立する技術」だとわかったら、次に気になるのは、「実際に、速読でどんな良いことがあるのか?」ということではないでしょうか。
- 勉強や資格試験にどう活かせるのか?
- 情報処理のスピードや記憶力に効果があるのか?
- 忙しい日常の中で、どう役立つのか?
そうした疑問にお応えするため、次の記事では、速読がもたらす具体的な効果とメリットを詳しく解説します。
👉 【次のステップへ】速読の効果とメリットを見る
速読とは?初心者のための「理解できる速読」入門ガイド」へ戻る
よくあるご質問(FAQ)
A:はい、可能です。
速読は「ただ速く読む技術」ではなく、理解度を保ったまま読書スピードを高める読書法です。特に初心者は、黙読(内音声化)のスピードを少しずつ上げていくことによって、無理なく理解しながら速く読めるようになります。むしろ、一定のスピードで読むことで集中力が高まり、理解度が上がることもあります。
A:いいえ、消す必要はありません。
むしろ、速読では“内音声化”は自然な働きであり、それを無理にやめると理解力が下がる原因になります。大切なのは、音を消すことではなく、頭の中で聞こえるスピードを上げること。内音声のテンポを高めていくことで、自然と読書スピードも上がり、理解力もキープできます。
詳しくは⇒内音声化のスピードを速くするトレーニングをご覧ください
A:そんなことはありません。
速読は特別な才能ではなく、視野や視点の使い方、脳の処理リズム、集中力の保ち方など、読書に関わるスキルを組み合わせて育てていく技術です。トレーニングを重ねれば、誰でも「理解しながら速く読む」力は伸ばせます。構造をつかんで読むコツさえ掴めば、再現性は十分にあります。
著者プロフィール

渡辺篤志:「株式会社いろどり」代表 「速読研究会」主宰
100冊以上の速読術・読書術・勉強法を学び、「これなら誰にでも習得できる」という独自のトレーニングメソッドを作り上げ、10年以上に渡り2000名以上に指導。著書に「身につく速読、身につかない速読 ~1冊1時間を目指す、挫折知らずの現実的速読トレーニング~」がある。