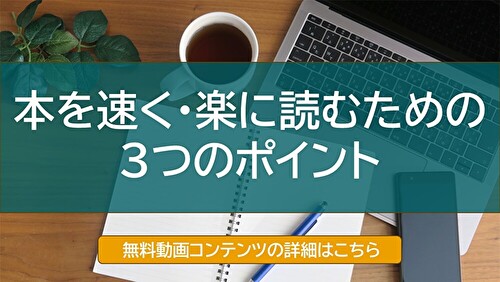はじめに:社会人の資格勉強は、時間との戦い
働きながら資格を取る・・・この言葉の裏には、簡単には言い尽くせない現実があります。日中は仕事に追われ、夜は疲れて机に向かえない。週末は家事や家族との時間に追われ、思うように勉強が進まない。
それでも「もう一度学び直したい」「自分の専門性を高めたい」と思う人は多いでしょう。私自身、40代で再出発し、行政書士・介護福祉士・社会福祉士・ケアマネージャー・日商簿記2級の5つの資格を取得しました。
資格を取ることは、単なるキャリアアップではありません。私にとっては「人生を立て直すための手段」であり、「再び社会に自分の居場所をつくる」ための挑戦でもありました。
そして、その過程で痛感したのは、「勉強の内容より、勉強のやり方を学ぶことの方が、はるかに重要」だということです。
本記事では、実体験に基づいた“働きながら合格するための勉強法”と、資格勉強を「人生の学び」に変える視点を、ストーリー形式でお伝えします。
起業の失敗から、介護の現場へ~再出発のきっかけ
私はもともと、資格とは無縁の人生を歩んでいました。30代のはじめに自然食品店を立ち上げ、「好きなことを仕事に」と意気込んで起業しましたが、経営の現実は厳しく、数年後には事業を畳むことに。
その後、再就職を試みましたが、年齢はすでに40歳手前。履歴書を送っても返事はなく、40件ほど応募しても面接にすら進めませんでした。
「資格として書けるものが何もない」。その事実を突きつけられました。どれだけ想いがあっても、社会的に証明できる“形”がない。自分の会社で経理や決算書作りを自分でやっていたので、基本的な簿記の知識はあったのですが、「簿記3級」すら取っていなかったので、履歴書には書けません。
だんだん精神的にも追い詰められてきた頃に出会ったのが、「働きながら資格が取れる」という介護人材育成プログラムでした。未経験からでも始められる仕事。学びながら経験を積める環境。それが、今につながる私の第二のキャリアのスタート地点でした。
介護の現場で、まず取らなければいけないのが「介護職員初任者研修」というもの。週に2日介護施設で下働きのような仕事をしながら(資格を持っていないと、実際の介護業務はできないため)、週に3日研修に通うという生活を半年ほど続けました。
そして、研修終了と同時に、その介護施設で正規職員として働き始めたのです。そして「介護・福祉の世界で生きていくなら、通用する力をつけよう」と思いました。「とれる資格はすべて取ってやろう」と。
それが、資格取得への動機だったのです。前の就職活動で苦しんだということももちろんありましたが、「資格試験の勉強をすることが、直接的に仕事のスキルアップにつながる」という実感があったのです。
働きながら勉強を続けるコツ:完璧を目指さず“仕組み”で進める
まず取得したのが、簿記2級です。介護の仕事には直接関係ありませんが、就職活動中に「とりあえずすぐに取れそうなも資格」として勉強を始めていたので、この際取っておこうと思ったのです。
次に取り組んだのが行政書士。当時は介護の仕事をずっと続けていくつもりはなく、「認知症の方のための成年後見人」などの仕事に感心があり、法律系の資格を取ろうと思ったのです。
しかし、当然ですが「簿記2級」とは比較にならない勉強量で、この時の経験が私の「勉強法」の原点になっており、この記事のベースになってます。
介護の現場は体力も気力も使う仕事です。夜勤明けに本を開いても、文字が頭に入らない。休みの日に図書館に行っても、眠気に負けてしまう。
最初は、テキストを丁寧に読み込み、線を引いて覚えるという王道の方法を取っていました。でも、現実は厳しかった。いくら読んでも、確認テストをすればほとんど正解できない。読んだページ数と成果がまったく比例しない。
そのとき、初めて自分の中で「勉強の限界」を感じました。そして気づいたのです。「自分は“勉強法”を知らないまま、努力だけで乗り切ろうとしていた」
これは多くの社会人が陥る落とし穴です。根性でカバーしようとしても、続かない。仕事をしながら勉強を続けるには、“意志”ではなく“仕組み”が必要なのです。
私がその後、どんなに疲れていても勉強を続けられたのは、意志を燃やしたからではなく、勉強の習慣をシステム化したからです。
勉強のやり方を学ぶことが、最短の合格法だった
私は「勉強法を勉強する」ことから始めました。自己啓発書、勉強術の本、合格者の体験記——とにかく手当たり次第に読みました。その結果たどり着いたのが、「インプット3割・アウトプット7割」の法則でした。
インプットの目的は“全体像をつかむ”こと
最初にテキストを読んで内容を覚えようとするのは無謀です。人間の脳は、構造や関連性が見えない情報を記憶できませんし、試験まで時間があるので「絶対に忘れる」からです。
それよりも、テキストを読むのは地図を描くように全体を俯瞰するため。「その試験ではどういうことを学ぶのか」「どんな専門用語があるのか」などを、ざっくり大まかに頭に入れる程度です。
この段階では、速読は大変役に立ちます。理解よりも「全体の流れ」を掴むことを優先しました。そして、ここで大事なのは、覚えようとしないことです。「わからなくてもいい」「一度で覚えなくていい」。この余白を持つことで、次の段階、アウトプットが活きてきます。
アウトプットで“できる”を増やす
次に、過去問を徹底的に繰り返します。最初はほとんど不正解でも構いません。私は正解した問題に大きな×印をつけ、×がついていない問題=まだ理解できていない問題として扱いました。「全部の問題に×がつくまでやる」このルールを守るだけで、勉強の迷いがなくなります。
ノートまとめは一切しませんでした。ノートをきれいに書くことが目的になってしまうからです。時間をかけてノートを作っても、それだけで覚えることは不可能で、結局読み返すことになる。だったらテキストを読み返すのと同じで、時間の無駄でしかありません。
その代わり、「できるまで過去問を回す」ことに徹底的に集中しました。この勉強法を実践すると、“わからない”が“わかった”に変わる瞬間が増えていきます。この小さな成功体験の積み重ねが、合格への推進力になるのです。
行政書士と介護福祉士—試験の性格がまるで違う
私は5つの資格を取得しましたが、その過程で強く感じたことがあります。資格試験には「落とすための試験」と「受からせるための試験」があるということです。
行政書士はまさに「落とすための試験」。細かい知識、曖昧な表現の違い、引っかけ問題…とにかく受験者をふるいにかける構造になっています。
一方で、介護福祉士や社会福祉士、ケアマネージャーなどの福祉系資格は「受からせる試験」。出題傾向は安定しており、基本を確実に押さえれば合格できます。
この違いを理解せずに「すべての試験を同じように勉強しよう」とすると、うまくいきません。行政書士のような試験では、理解の深さと正確さが命。一方、福祉系の試験では、広く浅く、基礎を取りこぼさないことが重要です。
さらに、私は受けたことがないのではっきりという事はできませんが、司法試験・会計士・税理士などの論述のある試験では、「知っている」だけではなく、「知識をベースに考えを組み立てる力」が求められるのでしょう。
つまり、試験の性格に合わせて、勉強法を変えること。これが複数の資格を通じて学んだ、とても大きなポイントです。
試験直前期は、“心を整える時間”にする
それから大切なのは、全体のスケジューリングです。特に、試験1か月前までには一通り勉強を終わらせることができるようにしておくことが大切。試験前の一カ月は新しいことはやらず、×で消し込んだ「分かった問題」も含めて全体の復習を繰り返すこととメンタル調整。
この、「メンタル調整」がとても大切で、焦りや不安が出てくる時期ですが、私は“心の整え方”を重視しました。
- 1か月前には「これで十分」と思える状態にしておく
- 当日は「当然のように受かっている自分」をイメージする
- 落ちるかもしれない、ではなく「もう受かっている」という感覚で臨む
このメンタル設計は意外と重要です。自己啓発の世界では、よく「思考が現実化する」とか「思っていることが引き寄せられる」という事が言われていますが、「合格する人は、試験前にすでに合格している」という言葉の意味が、ようやくわかりました。
資格勉強は「学び方を得る場」。合格は通過点にすぎない
合格通知が届いた時、もちろん嬉しさはありましたが、“歓喜”というものでは全然ありませんでした。「やっぱり受かっていた、そりゃそうだよね」という気持ち。このように書くと傲慢に聞こえるかもしれませんが、「受かって当然」というメンタル調整をしていたので、確信があったのです。
自分の中に“再現性のある学び方”ができていた、ということも大きいです。ある意味、試験の成否よりも、「学び方を身につけた」こと自体が最大の成果でした。
実際、行政書士試験の後に受けた介護福祉士、社会福祉士、ケアマネージャーの試験は、試行錯誤することなく極めて効率的に勉強できたと思っています。
そしてもう一つ、どうしても伝えたいことがあります。それは、資格勉強を「試験のための勉強」にしないこと。たとえば介護福祉士の勉強をしているとき、私は常に「この知識を現場でどう使うか」を意識していました。実際に働くようになると、試験で学んだ内容が驚くほど役立ちます。
ところが現場では、「それ、介護福祉士の試験で出たよね?」というような基本を知らない人が少なくありません。おそらく、「試験のためだけに勉強した」結果でしょう。試験が終われば、知識も消える。それではもったいない。
資格試験こそ、専門性を体系的に学ぶ最短ルートです。資格を「取ること」が目的ではなく、「学んだ知識をどう使うか」に焦点を当てる。それが、真の意味での“学び直し”です。
資格はゴールではなく、「何をどう学ぶか」を身につけるための通過点。この考え方が、私の人生を根本から変えました。
今、資格に挑戦するあなたへ
資格は“魔法の紙”ではありません。けれど、“自分を再構築するきっかけ”にはなります。必要なのは、強い意志よりも仕組み化された勉強法。
人は感情では続かない生き物です。だからこそ、「仕組みで続ける」こと。
- スケジュールを作る
- アウトプット中心に学びを回す
- 定期的に復習の仕組みを組み込む
- 受かっているというイメージを持つ
などを意識することで、学びは必ず積み重なっていきます。
「学び方を学ぶ」こと。それができれば、どんな時代でも、自分の人生をデザインできます。
学びの効率を一気に高める。「速く・楽に読む」3つのポイントを体験しよう
資格勉強でも、読書でも、「時間が足りない」「内容が頭に入らない」と感じる瞬間はありませんか?多くの人が、知識や勉強法を変えようとしますが、実は“読む力”そのものを整えることが、最も大きなブレークスルーになります。
私がこれまで資格勉強を通して痛感したのは、「読むスピード=理解の質」だということ。極端な高速では当然理解度は下がりますが、かといってゆっくり読めばいいかというと、そうでもないのです。速く読めるほど、全体像をつかみやすくなり、アウトプットにもつながりやすくなります。
そこで、あなたにも体験してほしいのが、無料動画コンテンツ『本を速く・楽に読むための3つのポイント』。この動画コンテンツでは、
- 文字を“かたまり”で捉える
- 視野を広げて“かたまり”を大きくする
- 視点の移動スピードを高める
という3つのコツを実演しながら解説しています。さらに、すぐ実践できる「3つのポイント実践ワーク」もプレゼント。
“読む力”が変われば、学びのスピードも確実に変わります。今すぐ、あなたの読書と勉強を進化させましょう。
資格試験の勉強が続く人と続かない人との違いは?
このページでは、著者自身の体験を踏まえて、資格試験の勉強法についてまとめました。ところで、資格試験の勉強で最大の敵は「勉強が続かない」という問題です。次のページでは、勉強を続けるためのコツをお伝えします。
👉【次のステップへ】資格勉強が続く人・続かない人の違いへ進む
よくあるご質問(FAQ)
A:意志ではなく「仕組み」で続けることです。スケジュールを作る、アウトプット中心に学びを回す、定期的に復習の仕組みを組み込む、受かっているというイメージを持つという意識が大切です。
A:目安は「インプット3:アウトプット7」。最初は全体像を速く掴み、細部は演習で“できる”に変えます。ノート作りに時間をかけすぎないのがコツです。
A:行政書士などの「落とす試験」は細部の正確さと深い理解を重視。介護福祉士・社会福祉士・ケアマネなどの「受からせる試験」は基礎の取りこぼし防止と範囲の網羅性を優先します。
A:新規学習は止め、過去問の反復で弱点潰しに集中。本番を想定したルーティンと「合格して当然」というメンタル設計で不安を下げます。
A:常に「現場でどう使うか」の視点で学ぶこと。資格試験は専門知識を体系的に学ぶ最短ルートです。合格後の実務で使い、知識を定着させましょう。
著者プロフィール

渡辺篤志:「株式会社いろどり」代表 「速読研究会」主宰
100冊以上の速読術・読書術・勉強法を学び、「これなら誰にでも習得できる」という独自のトレーニングメソッドを作り上げ、10年以上に渡り2000名以上に指導。著書に「身につく速読、身につかない速読 ~1冊1時間を目指す、挫折知らずの現実的速読トレーニング~」がある。
速読研究会サイトマップ
- 速読研究会トップページ
- やさしい速読動画講座
- 速読とは?初心者のための「理解できる速読」入門ガイド
- 速読トレーニングの方法
- 速読と仕事・キャリア
- 速読と資格試験・勉強法
- 社会人が働きながら資格に合格する勉強法|資格取得で学んだ“続ける仕組み”👈(現在のページ)
- 資格勉強が続く人・続かない人の違い
- 資格試験のテキスト読書法~合格者が実践する“効率的な読む技術”
- 勉強時間がない人のためのスキマ時間戦略
- ノート作りは時間の無駄?忙しい社会人のための最短合格アウトプット法
- 速読と読書術
- 速読と記憶術
- 速読の科学的根拠と研究
- 速読と語学学習
- 速読と健康・ライフスタイル
- 速読に関するQ&A
- 速読の練習におすすめの本・教材
- 速読講座・速読スクールの比較
- プライバシーポリシー
- 利用規約
- 特定商取引法に基づく標記
- お問い合わせフォーム
- 運営者プロフィール