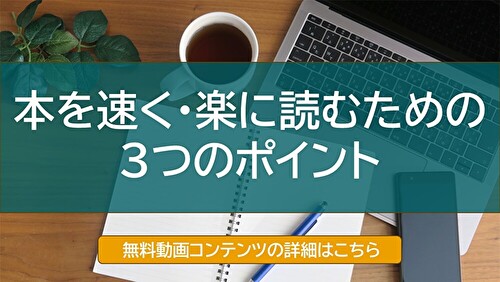なぜ「続けること」がこんなに難しいのか
資格試験の勉強を始めるとき、多くの人が「今度こそは」「次こそは」と決意します。しかし、日常に追われるうちに気づけば本を開かなくなり、気持ちばかりが焦っていく。そんな経験を、あなたも何度かしてきたのではないでしょうか。
続かない理由を「意志の弱さ」や「忙しさ」のせいにしがちですが、本当の原因はもっと深いところにあります。それは、学びの設計図がないまま走り出してしまうことです。
勉強とは、気合いで乗り切るマラソンではありません。それはむしろ、感情・目的・環境の3つをデザインしていくプロセスです。この3つを整えるだけで、努力の方向がそろい、驚くほど継続が楽になります。
なぜ資格勉強は続かないのか?
資格試験を挫折してしまう人の多くは、次の3つのパターンに陥っている可能性があります。
- 計画を立てずに、気分で勉強を始めてしまう
- 結果ばかり気にして、日々の小さな前進を評価しない
- 一気に詰め込もうとして、途中で燃え尽きる
これらに共通するのは、「設計よりも感情に頼っている」こと。もちろん、感情は大切です。しかし感情は“燃料”であって、“ハンドル”ではありません。
人間の感情は波のように上下します。やる気があるときもあれば、沈んでしまう日もある。その波に振り回されてしまう人は、走り出しても長く続かないのです。
一方で、続ける人は感情をコントロールするのではなく、活かしています。たとえば、「机に座る前にコーヒーを淹れる」「学習アプリを開いたら音楽を流す」など、自分の“スイッチ”を設計しているのです。
感情を排除するのではなく、「始めるきっかけ」に使う。この小さな仕組みが、継続の分かれ道になります。
感情と目的をつなぐ「学びの設計」
もう一つ、勉強が続かない理由に「目的の曖昧さ」があります。「とりあえず資格を取っておきたい」という思いでは、途中で迷いが生まれやすかったり、「まあ、いっか」になりがち。
そうではなく、なぜその資格を取りたいのか。合格したあと、どんな仕事をして、誰に喜ばれたいのか。それを明確にしておくことが、モチベーションを持続させる鍵になります。
たとえば、
「介護福祉士として利用者さんの笑顔を増やしたい」
「簿記を学んで、将来自分のビジネスを安定させたい」
そんな“資格の先にある物語”を描くことが、学習の原動力になります。
試験に「受かること」自体を目的にすると、合格発表で終わってしまいます。でも、「その資格を活かしてどんな未来を生きるか」を描けば、勉強は「人生のデザイン」に変わります。
合格はゴールではなく、通過点。本当の目的は、資格を通して“自分の専門性を育てること”なのです。
合格者が実践している「学習ロードマップ」の描き方
では、続ける人はどんなふうに勉強を設計しているのでしょうか。彼らに共通しているのは、逆算思考です。「試験日」から逆算して、「今日やること」を決めています。
私自身も、資格試験の勉強をするときは、必ずこの考え方を取り入れました。最初は「1日1時間できればいいや」と思っていましたが、試験日から必要な学習時間を逆算した瞬間に、考え方が変わりました。“今日の1時間”が、確実に“合格”へつながるという手ごたえを感じられたのです。
年間→月間→週間→日次へ分解する“逆算設計”
- 年間計画:
合格までに必要な勉強量を算出します(例:テキスト1000ページ、問題集500ページ)。インターネットなどで調べると「標準的な学習時間」が出てくることがありますが、「学習時間」で考えるより「学習量(ページ数等)」で考える方が計画が立てやすいです。 - 月間計画:
試験までの日数を考え、1カ月当たりのボリュームを考えます。学習量÷試験までの月数+1カ月で計算すれば、1ヵ月でどれぐらい進める必要があるかの目安が分かります。1カ月プラスするのは、試験の1カ月前には一通り全部終わっているという状態にするためです。 - 週間計画:
月間計画ができたら、「今週はどこまで進めるか」が具体的に見えてきます。「何ページから何ページ」と決めてもいいですし、「第〇節と第〇節」というように項目ごとでもいいでしょう。Todoリストのアプリなどに今週勉強する項目を書いて置き、「終わったら消していく」という方法が、モチベーションを保つ上でもお勧めです。一週間のうち最低1日は何も予定を入れない「予備日」を作っておきましょう。 - 日次計画:
朝20分、夜10分など、無理なく続けられるリズムを作りましょう。週間計画から「今日行うこと」を確認します。
このように分解すると、「今日何をすべきか」が明確になります。そして、達成できた日には、しっかりと“自分を認める”ことが大切です。小さな達成の積み重ねが、学習の推進力になります。
「インプット3割・アウトプット7割」の勉強黄金比
学習において最も効率的なのは、「理解3割・実践7割」のバランスです。多くの方が「テキストを線を引きながらしっかり読み込む」ことをメインに考えてしまいますが、この勉強の仕方は時間を掛けた割に頭に残りません。
記憶は、インプットの時ではなく「アウトプットすることで定着する」のです。
テキストを読むのは全体像を俯瞰するため
テキストを読むのは、最初にザっと全体像を見渡す時だけで問題ありません。覚えようとする必要もありません。一生懸命読んで覚えようとしても、試験までには忘れてしまうので、ほとんど意味がないのです。
一般的な本を読むときであれば、2回3回繰り返し読む事で、ある程度の内容が頭に入りますが、試験では正確な知識を広範囲にわたって頭に入れる必要があり、読むだけでは不十分なのです。
勉強法のメインはアウトプット
だからこそ、資格試験の勉強では「インプット」よりも「アウトプット」をメインにする必要があるのですが、ここでアウトプットのやり方を間違えると、挫折の原因になります。
最も効率的なアウトプット=過去問を解く
社会人にとって、最も現実的で効果的なアウトプットは「過去問」です。忙しい日々の中で勉強を継続するには、手法をシンプルにすることが大切。
様々な勉強法で「ノートの作り方」が指南されていますが、現実問題としてノートを作ろうとすると勉強量が膨大になり、途中で息切れするリスクが跳ね上がります。
勉強素材は「基本テキスト+過去問」に絞りましょう。この2つだけで、だいたいの試験では試験範囲の8割~9割をカバーできます。
過去問を繰り返すうちに、頻出分野や自分の苦手が自然に浮かび上がります。“闇雲に頑張る勉強”から、“効率よく成果を出す勉強”へと変わるのです。
過去問の後、余裕があれば、“仕事で使える知識”に変える要約をする
過去問を一通り解き終え、余裕があったら次の段階に進みましょう。それは、「学んだ知識をどう使うか」を考えることです。
たとえば、
「この考え方は現場でどんな判断に活かせるだろう?」
「この知識を人に説明するなら、どんな言葉が伝わりやすいか?」
そんな意識を持つことで、知識が“現実で使える知恵”に変わっていきます。
試験勉強の目的は、「点数を取ること」ではなく「自分を成長させること」。合格後のあなたの仕事の質を高めるためにも、この“第2のアウトプット”がとても効果的です。
習慣化を支える「感情と環境の設計法」
では、どうすれば日々の勉強を“当たり前”にできるのか。
ここで鍵になるのが、「感情と環境の設計」です。勉強が続かない人と続く人の差は、意志力ではなく“仕組みの違い”です。以下の10の観点を見比べてみてください。自分の思考や行動の癖が、どちらに近いかを感じ取るだけでも、行動の方向が変わります。
続かない人と続く人の10の違い
- 感情の扱い方
続かない人は「気分が乗らない」と勉強を止めてしまいます。
続く人は、気分を整える“スイッチ”を持っています。
朝のコーヒー、好きな音楽、机に座る儀式……。感情を行動の合図に変える人は、気分の波に左右されません。 - 目的の持ち方
続かない人は「合格」をゴールにします。
続く人は「資格を活かしてどう生きたいか」をゴールに置きます。
“未来の物語”があると、今日の努力が意味を持つのです。 - 学びの捉え方
続かない人は“詰め込み型”。
続く人は“使う前提”で学びます。
「この知識を誰にどう説明するか」を意識すると、理解も記憶も深まります。 - 時間の使い方
続かない人は「時間があればやる」。
続く人は「やる時間を先にブロック」します。
予定表に“学習の予定”を入れ、他の予定をその周りに組むのです。 - 完璧主義の罠
続かない人は“すべて完璧に”を目指し、重圧で止まります。
続く人は“7割主義”。
「完璧より継続」を合言葉に、毎日の小さな達成を積み重ねます。 - 失敗の捉え方
続かない人は「中断=失敗」と考えます。
続く人は「また戻ればいい」と考えます。
1日休んでも、翌日戻ればOK。再開のルールを決めておく人は強い。 - 記録の仕方
続かない人は“できなかった日”ばかりを見る。
続く人は“できた日”を積み上げる。
ノートに書いたチェックマークが自信の証になります。 - 環境の整え方
続かない人は、毎回違う場所・時間で勉強します。
続く人は、同じ机・同じ時間・同じ道具を使います。
脳は「同じ刺激」を受けると“習慣モード”に切り替わるのです。 - 思考のリズム
続かない人は考えすぎて動けません。
続く人は「とりあえず5分だけ」から始めます。
動きながら考える人は、止まらずに修正できます。 - 支えの持ち方
続かない人は一人で抱え込みます。
続く人は、仲間・コーチ・ツールを活用します。
人に話すことで、学びは整理され、行動は継続します。
これらの違いは、どれも“根性論”ではありません。意志が弱くても、仕組みを作れば続けられます。そして仕組みを回すうちに、「続けられる自分」への信頼が育ちます。
今日から始められる3ステップ
- 時間を決める。
「朝の15分」「夜の10分」と、まず時間を固定。
“やる気”ではなく“時間”がトリガーになります。 - 場所を決める。
家の中の“勉強ゾーン”を決めましょう。机の上の一角で十分です。
場所が変わらないことで、脳が“勉強モード”を学びます。 - 記録する。
今日取り組んだ単元を書き出す。
ノートに増えるページが自信になります。
または、ToDoリストを消していく達成感を味わいましょう。
この3つを繰り返すだけで、“やらなきゃ”が“やりたくなる”に変わります。
まとめ:続ける人が持っているのは「根性」ではなく「設計図」
努力は、量より構造です。続く人は、意志の力ではなく“習慣の設計”で前に進んでいます。1日15分でも構いません。小さな時間を「積み重ねる仕組み」に変えるだけで、半年後には見える景色が変わります。
資格試験は、人生の通過点です。その先にある「自分らしい専門性」を磨くために、今日の一歩を丁寧に重ねていきましょう。
読書スピードを上げて、「勉強が続く人」へステップアップしよう
資格勉強や仕事の学びを続けるためには、「時間の使い方」を変えるだけでなく、“読み方そのもの”を変えることが大きな鍵になります。どんなに計画を立てても、テキストを読むのに時間がかかりすぎては、集中力も続かず、復習のリズムも崩れてしまうからです。
そんな悩みを解決するために、私が無料でお届けしているのが、動画レッスン「本を速く・楽に読むための3つのポイント」です。
この動画では、
- 文字をかたまりで捉える
- 視野を広くしてかたまりを大きくする
- 視点の移動スピードを速くする
という3つのコツを、実際の映像と実演でわかりやすく解説しています。
さらに、動画と一緒にダウンロードできる「3つのポイント実践ワーク」では、すぐにトレーニングできるシート付き。
忙しい社会人でも、1日5分で“速く・深く・楽に読む力”が身につきます。
資格試験のテキストをどう読むか?
このページでは、資格試験の勉強が続く人と続かない人との違いを見てきました。次のページでは、実際にどのように資格試験のテキストを読めばいいか、お伝えします。
👉【次のステップへ】資格試験のテキスト読書法~合格者が実践する“効率的な読む技術”へ進む
よくあるご質問(FAQ)
A:「朝15分」「通勤中15分」など短時間を“固定枠”にし、先に予定表へブロックします。余り時間でやろうとせず、時間→行動の順で決めると継続しやすくなります。
A:完璧主義を手放し「7割主義」に。再開儀式(机に座る→タイマー3分→過去問1問)を決め、まず“再開できる設計”を用意しましょう。
A:「過去問を解く」が最短ルートです。基本テキスト+過去問に絞り、①過去問→②間違い分析→③頻出テーマの補強→④再トライのループで回すと伸びます。
A:「今日の単元をノートに一行で記録」または「Todoリストを消し込み」。増えるページや消し込みの達成感が自己効力感を高め、継続の推進力になります。
A:役立ちます。テキストをかたまりで捉え、視野を広げ、視点移動を速めると理解スピードと復習効率が向上します。基礎は無料動画「本を速く・楽に読むための3つのポイント」で実演解説しています。
著者プロフィール

渡辺篤志:「株式会社いろどり」代表 「速読研究会」主宰
100冊以上の速読術・読書術・勉強法を学び、「これなら誰にでも習得できる」という独自のトレーニングメソッドを作り上げ、10年以上に渡り2000名以上に指導。著書に「身につく速読、身につかない速読 ~1冊1時間を目指す、挫折知らずの現実的速読トレーニング~」がある。
速読研究会サイトマップ
- 速読研究会トップページ
- やさしい速読動画講座
- 速読とは?初心者のための「理解できる速読」入門ガイド
- 速読トレーニングの方法
- 速読と仕事・キャリア
- 速読と資格試験・勉強法
- 社会人が働きながら資格に合格する勉強法|資格取得で学んだ“続ける仕組み”
- 資格勉強が続く人・続かない人の違い👈(現在のページ)
- 資格試験のテキスト読書法~合格者が実践する“効率的な読む技術”
- 勉強時間がない人のためのスキマ時間戦略
- ノート作りは時間の無駄?忙しい社会人のための最短合格アウトプット法
- 速読と読書術
- 速読と記憶術
- 速読の科学的根拠と研究
- 速読と語学学習
- 速読と健康・ライフスタイル
- 速読に関するQ&A
- 速読の練習におすすめの本・教材
- 速読講座・速読スクールの比較
- プライバシーポリシー
- 利用規約
- 特定商取引法に基づく標記
- お問い合わせフォーム
- 運営者プロフィール