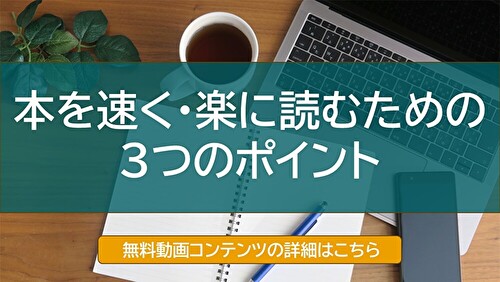- 速読は「学生だけのスキル」ではない
- 「なんとなく読む速読」では仕事にならない
- 営業職・管理職|情報処理と判断スピードを高める
- 弁護士・法務|膨大な契約書や判例を扱う
- コンサルタント・マーケター|大量の情報から洞察を得る
- 教師・教育関係者|教材研究や答案チェック
- 医師・医療従事者|最新知識を臨床に活かす
- 研究者・大学院生|論文レビューや研究準備
- ライター・編集者・ジャーナリスト|情報収集と原稿確認
- ITエンジニア・SE|仕様書やマニュアルの確認
- 資格試験を目指す社会人|短期間で成果を出す
- 投資家・アナリスト|情報をもとに迅速に判断
- 起業家|幅広い分野の知識を吸収する
- あなたの仕事にも必ず速読の出番がある
- まずは「3つのポイント」から実感してみませんか?
- 速読がどのように生産性向上に役立つか?
- よくあるご質問(FAQ)
- 著者プロフィール
- 速読研究会サイトマップ
速読は「学生だけのスキル」ではない
「速読」と聞くと、どんなイメージが浮かぶでしょうか。多くの人は「受験生が試験勉強に使うもの」とか、「資格試験で一夜漬けする社会人のためのテクニック」を思い浮かべるかもしれません。
あるいは、昔ブームになった「右脳速読法」のような、「ページをパラパラめくるだけで内容が頭に入る」といった怪しげなイメージを抱いている人もいるでしょう。
でも、本当の速読はそうした一部の人のためだけのものではありません。むしろ、毎日の仕事で何十通ものメールに目を通し、分厚い会議資料を読みこなし、契約書やマニュアルを正しく理解して判断を下している、そんな普通のビジネスパーソンにこそ役立つスキルなのです。
情報が溢れる時代に、私たちの「読む力」は、もはや勉強のためだけでなく、仕事やキャリアの成果を左右する武器になっています。
「なんとなく読む速読」では仕事にならない
ただし、ここで一つ大事なことをお伝えしておきます。仕事で扱う文書は「正確に理解すること」が前提です。小説や自己啓発書を読むときには「雰囲気をつかむ」だけの読み方もありでしょう。でも契約書やマニュアルを「なんとなく」理解するだけでは、重大なミスにつながります。
だからこそ、実務で役立つ速読には次の3つの観点が欠かせません。
1. 「右脳速読」や「潜在意識速読」は役に立たない
昔流行した「右脳で写真のようにページを記憶する」といった速読法は、現実には実務で使えません。確かに速くめくれば「読んだ気」にはなるかもしれませんが、仕事は「正確な理解」と「根拠のある判断」が求められます。
2. 内音声化はむしろ必須
「速読するなら頭の中で声に出さない方がいい」と言われることがあります。でもこれは半分正解で、半分は誤解です。
確かに内音声化が遅すぎると読書スピードは落ちます。けれども、完全に音を消してしまったら内容を正確に理解できません。実務で必要なのは「内音声化のスピードを速くする」つまり、「熟読のスピードを速くすること」なのです。
3. 読解力こそ速読の土台
文章をすべて同じスピードで読む必要はありません。重要なポイントと、そうでない部分を見極め、読むスピードに強弱をつける。その読解力こそが、本当の意味での「速さ」を支えています。
つまり、実務で役立つ速読とは「単なる速さ」ではなく「正確さと選別眼を伴った速さ」。これを理解しておくと、これから紹介する“職種別の速読活用シーン”がぐっとリアルに感じられるはずです。
営業職・管理職|情報処理と判断スピードを高める
それでは、ここから「職種別・速読が役に立つ場面」を見ていきましょう。
営業や管理職にとって、一日は情報の洪水との戦いです。朝一番、メールボックスを開いた瞬間に数十通のメールが並んでいる。その中にはお客様からの重要な連絡もあれば、社内のCCで届いた参考程度の情報も混ざっている。
もし全部を同じテンポで読んでいたら、それだけで午前中が終わってしまうでしょう。
速読を身につけると、この「仕分け」が劇的に速くなります。2~3秒で「これは即対応」「これは後で確認」「これは削除」と判断できるのです。その分、本当に大事な案件に集中できます。
会議資料も同じです。100ページに及ぶ分厚い資料を全部精読していたら、会議の前に力尽きてしまいます。速読なら「全体の流れ」を短時間でつかみ、重要なデータだけに注目して深掘りできます。結果として、会議中に的確な意見を言えるようになり、意思決定のスピードも増すのです。
「時間が足りない…」と悩んでいる管理職ほど、速読を味方にすべきだと思います。
弁護士・法務|膨大な契約書や判例を扱う
法務の世界は、一字一句の解釈が命取りです。だから「速読なんて危ないのでは?」と思われるかもしれません。
でも実際には、速読こそが武器になります。
たとえば契約書。100ページに及ぶものも珍しくありません。そのすべてを同じテンポで読んでいては、案件処理が追いつきません。
速読を活用すると、まず全体像を数分でつかみ、重要条項やリスクがありそうな部分を素早く特定できます。
そのうえで、その箇所だけ丁寧に読み込む。この「読み分け」の技術があれば、スピードと正確さを両立できるのです。
判例調査や文献レビューも同じ。膨大な資料の中から「該当する部分」を瞬時に見つけ出すことができれば、依頼人にとっても大きな価値となります。
コンサルタント・マーケター|大量の情報から洞察を得る
コンサルタントやマーケターの仕事は、情報の山から“宝石”を探し出す作業です。市場調査レポート、統計資料、業界ニュース…。読むべき資料は毎日のように積み上がり、机の上が紙の山になることも。
速読が使えると、その山を「短時間で俯瞰」できるようになります。全体をざっと読み、大事な数値やトレンドを拾い出し、比較整理する。そうすれば、分析や提案により多くの時間を割けます。
クライアントの前で「最新のデータを踏まえると、こういう戦略が考えられます」と即座に言える人。その裏には、速読によって生まれた情報処理力があるのです。
教師・教育関係者|教材研究や答案チェック
教師は、授業準備だけでも膨大な読み物に向き合います。教材、教育論文、生徒のレポート…。すべてを丁寧に読んでいたら、睡眠時間が削られてしまうほどです。
速読を取り入れると、教材研究を短時間で終えられるようになります。「どの部分を授業で使うか」「どの資料が生徒にわかりやすいか」を見極めるのが速くなるのです。
さらに、生徒の答案を速く読めるようになれば、フィードバックに時間を回せます。“量”を処理する速読が、“質”を高める教育につながるわけです。
医師・医療従事者|最新知識を臨床に活かす
医療現場は日々進化します。新しい論文やガイドラインが次々に発表され、医師や看護師は学び続けなければなりません。ですが忙しい診療の合間に、分厚い専門誌を隅々まで読むのは不可能です。
ここで速読が役立ちます。論文の概要を素早く読み取り、必要な部分だけ丁寧に確認する。そのスキルがあれば、最新の知識を診療にいち早く反映できます。
「医師は一生勉強」と言われますが、その勉強を支えるのが速読なのです。
研究者・大学院生|論文レビューや研究準備
研究者にとって最大の課題のひとつは「時間との戦い」です。関連研究を把握するために何十本もの論文を読む必要がありますが、1本を精読するだけで数時間かかることも。
速読を身につけると、まず全体の要旨を数分で押さえられるようになります。そのうえで必要な部分を精読することで、効率と正確さを両立できます。
また、速読があれば隣接分野の論文にも幅広く目を通せます。思いもよらないアイデアや研究テーマが浮かぶことも珍しくありません。
ライター・編集者・ジャーナリスト|情報収集と原稿確認
ライターや編集者の仕事は「読む」と「書く」の繰り返しです。取材メモ、参考資料、過去記事…。それらを短時間で理解できるかどうかで、記事の質も締め切りのストレスも変わってきます。
速読を活用すると、情報収集のスピードが飛躍的に高まります。記事構成のためのアイデア出しもスムーズになり、執筆に集中できるのです。
さらに、原稿確認や校正作業もスピードアップ。「締め切り間際に徹夜でチェック」という状況から解放されるのは、まさに速読の恩恵です。
ITエンジニア・SE|仕様書やマニュアルの確認
エンジニアが頭を抱えるのは「必要な情報がどこにあるかわからないマニュアル」です。仕様書やドキュメントは膨大で、そのすべてを順に読むのは非効率です。
速読を使えば、まず全体の構造をざっと把握し、目的の情報を素早く探し当てられます。結果として、調査時間を大幅に減らし、開発や実装に多くの時間を使えるようになります。
「読むスピード」が「作るスピード」に直結する世界だからこそ、速読が効くのです。
資格試験を目指す社会人|短期間で成果を出す
働きながら資格試験に挑むのは本当に大変です。限られた時間で膨大なテキストを学び、過去問を解かなければなりません。
速読を取り入れると、テキストを短時間で処理し、繰り返し学習に時間を割けるようになります。理解と暗記のサイクルが速く回り、合格可能性がぐっと高まります。
「時間がない」という社会人受験生にとって、速読は強力な味方になるでしょう。
投資家・アナリスト|情報をもとに迅速に判断
投資の世界では、情報の鮮度が利益を左右します。ニュース記事や決算資料をいかに早く処理し、意思決定につなげられるかが勝負です。
速読を使えば、重要な数字やキーワードを素早く抽出できます。他の投資家より一歩早く動けることが、そのまま成果に直結します。
まさに「情報処理スピード=成果」の世界において、速読は欠かせないスキルなのです。
起業家|幅広い分野の知識を吸収する
起業家は、経営・マーケティング・資金調達・テクノロジー…と、多分野の知識を同時に扱わなければなりません。本やレポートを一冊ずつ丁寧に読んでいたら、学ぶべきことの半分も終わりません。
速読を身につければ、多様な分野の情報を短時間でインプットできます。結果として「学び→行動」までのスピードが速くなり、事業成長のスピードにもつながるのです。
あなたの仕事にも必ず速読の出番がある
ここまで見てきたように、速読は特定の職業だけのスキルではありません。「文章を読む場面」がある限り、どんな仕事にも応用できます。
ただし忘れてはいけないのは、実務では「正確な理解」が前提だということ。内音声化をベースに、読むメリハリをつけ、要点を見極める読解力を磨くこと。これこそが、キャリアの成果を支える本物の速読です。
まずは自分の仕事を振り返って、「どの場面で速読を使えるか?」を考えてみてください。その気づきが、キャリアを一歩前に進めるきっかけになるはずです。
まずは「3つのポイント」から実感してみませんか?
ここまで読んで、「速読は自分の仕事でも役立ちそうだ」と思った方へ。
実は、速読の効果を実感するために必要なのは、特別な才能や難しい訓練ではありません。文字をかたまりで捉える、視野を広くする、視点の移動をスムーズにする――たった3つのポイントを押さえるだけで、読むスピードと理解力は驚くほど変わります。
今回ご用意した無料動画では、この3つのポイントを実演でわかりやすく解説。さらに、ご自宅でそのまま練習できる「3つのポイント実践ワーク」もセットでお届けします。
まずは“速く・楽に読める感覚”を体験してみませんか?下のリンクから、今すぐ無料で受け取ってください。
動画では実演を交えてわかりやすく解説。さらに即実践できるワークシートもプレゼント。
時間を味方につけ、あなたのキャリアを加速させましょう。
速読がどのように生産性向上に役立つか?
このページでは、速読が役に立つ場面を職種別にみてきました。仕事をする上で、どんな場面でも速読のスキルが役に立つことを実感して頂けたと思います。
次は、速読がどのように「生産性向上」に寄与するかを見ていきましょう。
👉【次のステップへ】速読と生産性向上へ進む
よくあるご質問(FAQ)
A:使えます。前提は「正確さ>速さ」。①目的を決めて読む、②全体の構造を先に把握、③要点だけを素早く抽出、④必要箇所のみ精読、という“読み分け”がコツです。内音声化を保ちながら、重要度に応じてスピードを切り替えると誤読が防げます。
A:いいえ。契約書・仕様書・論文などは根拠ある理解が必須です。推奨は、プレビュー→目的設定→構造把握→要点抽出→根拠精読の5ステップ。非科学的な「速さ」だけはリスクになります。
A:実務では消さない方が安全です。完全に消すと意味の取りこぼしが増えます。音を“速く滑らかにする”訓練(語句をかたまりで捉える・視野を広げる・視線移動をスムーズにする)で、理解を保ったまま速度を上げられます。
A:3レイヤー読み(全体像→要点→根拠)を繰り返し、見出し・図表・結論を先読みして仮説を立てる→本文で検証、が効果的。会議資料・契約書用のチェックリストを用意し、キーワードにマーカーを入れて“読む基準”を固定化すると精度が上がります。
A:毎日の業務文書を“教材”にして取り組むのが最適です。メールは件名と冒頭数行で要点を掴む練習、会議資料はまず見出しと図表で全体像を把握する練習をする。さらに新聞や専門誌で「5分以内に要点を3つ抜き出す」訓練をすると、実務に直結する速読力が身につきます。
著者プロフィール

渡辺篤志:「株式会社いろどり」代表 「速読研究会」主宰
100冊以上の速読術・読書術・勉強法を学び、「これなら誰にでも習得できる」という独自のトレーニングメソッドを作り上げ、10年以上に渡り2000名以上に指導。著書に「身につく速読、身につかない速読 ~1冊1時間を目指す、挫折知らずの現実的速読トレーニング~」がある。