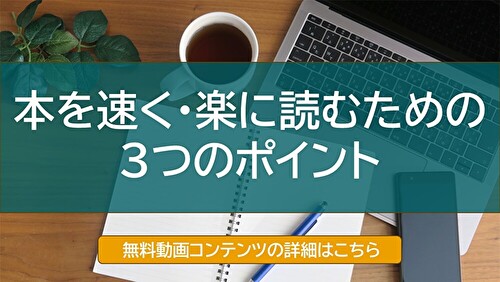はじめに:好きな本が最強のトレーニング教材
「もっと速く本が読めたらいいのに・・・」そう思ったことはありませんか?
でも、いざ“速読”を学ぼうとすると、難しそうな訓練や時間のかかる練習方法が出てきて、ちょっと身構えてしまう…そんな経験があるかもしれません。
でも実は、特別な教材やハードなトレーニングをしなくても、日々の読書の中で“読むスピード”は自然と高めていくことができます。その鍵になるのが、「好きな本」を使った読書習慣です。
速読の技術は、特別なスキルではなく、「読む経験の質と量」で磨かれていきます。そして、その“経験”をもっとも自然に積み上げられるのが、自分の興味や関心に合った「好きな本」を読むことなのです。
この記事では、前ページ「読解力を鍛えるトレーニング」で紹介した「意図・前提・行間を読む力」をベースにしながら、読むスピードと理解力の両方を伸ばす“普段の読書術”を具体的に紹介していきます。
なぜ「好きな本」を読むと速くなるのか?
読書スピードが上がらない原因は、「集中できない」「つまらない」「途中で飽きてしまう」といった読書体験の質にあることが多いです。逆に言えば、読むこと自体が楽しくて、先が気になる本を選べば、自然と読むスピードは上がっていきます。
理由1:先が気になって、どんどんページが進む
物語に引き込まれたり、知りたいテーマに夢中になったりすると、脳は“もっと読みたい”というモードになります。この状態では、読むスピードも自然と上がり、内容の吸収率も良くなるのです。
理由2:背景知識があると、読み飛ばし力がつく
好きな分野の本であれば、多少知らない用語があっても、文脈から推測して理解できます。この「推測力」は、速読の核心のひとつで、「すべてを丁寧に読まなくても意味がつかめる」読み方につながります。
理由3:集中力が切れにくい
嫌々読む本は、どんなにがんばっても集中力が持ちません。けれど好きな本なら、長時間でも没頭できる。これこそが“読む力”を鍛える理想的な状態です。
普段の読書で意識したい「3つの力」
前回紹介した読解力の3ステップを、改めてここで復習しましょう。
① 意図を探す視点
「この本はなぜ書かれたのか?」「筆者は何を一番伝えたかったのか?」という問いを持つことで、読書が“情報収集”ではなく“対話”になります。筆者の立場や背景を想像することで、読み方に深みが出てきます。
② 前提を読み取る姿勢
すべての文章は、ある前提のもとに書かれています。「これって当たり前?」と思えることに疑問を持つと、読書の視野が広がります。たとえば、「読書は良いことだ」という前提が疑問視されると、まったく違う読み方が可能になります。
③ 行間を味わう余裕
皮肉や比喩、暗示など、行間には多くの「書かれていない情報」が含まれています。「なんでこの表現を使ったんだろう?」という小さな気づきが、読書の楽しさを倍増させます。
この3つを意識することで、ただ読むだけでなく、「考えながら読む」力が養われ、速読との相乗効果が期待できます。
読書スピードが自然に上がる“3ステップ読み”トレーニング
ここからは、実際に速読力を高めるための具体的な読書トレーニング法をご紹介します。
初心者がスキーをするときに緩やかな斜面から始めるように、速読の練習でも「読みやすさ」が非常に大切です。
- 1行38~40文字、1ページ15~16行程度(文字が大きめ)
- 改行が少なく、文章が続いている構成
- 図解やイラストが少なく、1章あたり20~30ページ前後
- 見開きで完結するような短文形式ではなく、ある程度まとまりのある文章
こうした条件の本を選ぶことで、文章全体のリズムをつかみやすくなり、読み進める力がぐんと育ちます。
この“3ステップ読み”が、日常的に速読力を育てるコツです。
下読み
内容の理解は3割程度でもOK。やや速めのスピードで読み、何となくの雰囲気や構成をつかむことが目的です。速すぎて全くわからないのはNGですが、「少し負荷がかかるスピード」がベスト。
本番読み
通常のスピードで、しっかりと内容を理解しながら読みます。ここで読解力(意図・前提・行間)を意識すると、吸収力が格段に上がります。
仕上げ読み
再び速めのスピードで同じ章を読み直します。一度理解した内容なので、スムーズに読める感覚が得られます。これが「速く読んでも意味が取れる」という感覚を育ててくれます。
- 1章が20ページなら、3ステップで約30分
- この方法で1冊~3冊読めば、スピードも理解力も驚くほど変わってきます
- 同じ章を3回読むことで、自然に記憶の定着率も上がります
習慣化のアイデア
- 慣れてきたら、1冊全体を下読み→本番読み→仕上げ読みでもOK
- 本屋で「下読み」だけして、買うかどうか判断するのも◎(買う時はお礼も兼ねてそのお店で)
- 通勤前や昼休み、寝る前などに組み込めば習慣になりやすい
この読み方は、“努力感なく続けられる”という点で、最強の速読トレーニング法といえるでしょう。
ChatGPTを活用して読書の質をさらに高める
読んだ内容についてChatGPTに質問することで、理解を深めたり、別視点を得ることができます。
- 「この章の要点を一言で言うと?」
- 「この例え表現、どんな意味があると思う?」
- 「筆者の背景にどんな価値観がある?」
こうした問いを投げかけるだけで、読書が「対話」に変わります。これにより、自分ひとりでは気づけなかった観点を得ることができます。
まとめ:普段の読書が、読む力を育てる最短ルート
好きな本を、自分のペースで、3回読む。それだけで、あなたの読書力は確実に変わっていきます。
- 読解力が上がる
- 理解が深まる
- 読書スピードも自然に上がる
「好きなことを楽しむ」ことが、最も力になる——それは、読書においても同じです。
ぜひ今日から、“好きな本で読む力を育てる読書習慣”を始めてみてください。
読む力を、もっと自然に育てるために──「3つのコツ」を動画で体験してみませんか?
好きな本を読んでいく中で、「もっと楽に、もっと速く読めたら…」と思うことはありませんか?
そんなあなたのために、読書スピードと理解力を自然に高めるための【3つのポイント】をまとめた無料動画をプレゼントしています。
内容はとてもシンプルで実践的。
1:文字を“かたまり”で捉える
2:視野を広げて、一度に読む情報量を増やす
3:視点の移動スピードを意識して、リズムよく読む
それぞれのポイントを、わかりやすい実演つきで解説した動画と、すぐに試せるトレーニングワークもご用意しました。
“読むことが楽になる感覚”を、ぜひ体験してみてください。
速読と仕事・キャリア
ここまで、速読のトレーニング方法を見てきました。次からは、速読が普段の仕事やキャリアにどのように活用できるのか、見ていきましょう。
👉【次のステップへ】「速読と仕事・キャリア|情報過多時代の【読む力】が未来を変える」へ進む
よくあるご質問(FAQ)
A:はい。好きな本を読むと「集中力」「推測力」「継続力」が自然に高まり、速読に必要なリズムや理解力が身につきます。
特に、紹介している“3ステップ読み”を取り入れることで、楽しみながらスピードと理解力を両立できます。
A:同じ章を「下読み→本番読み→仕上げ読み」と3回読む“3ステップ読み”がおすすめです。
理解度3割でもOKな速読→内容重視の通常読書→スピードを上げて再読、という順で読むことで、速く読んでも内容がつかめる感覚が自然と身につきます。
A:初心者には、1ページ15~16行・1行38~40文字程度で、図が少なく、1章あたり20~30ページの構成の本がおすすめです。
文章のリズムをつかみやすく、下読み・本番読み・仕上げ読みの反復がしやすくなります。
著者プロフィール

渡辺篤志:「株式会社いろどり」代表 「速読研究会」主宰
100冊以上の速読術・読書術・勉強法を学び、「これなら誰にでも習得できる」という独自のトレーニングメソッドを作り上げ、10年以上に渡り2000名以上に指導。著書に「身につく速読、身につかない速読 ~1冊1時間を目指す、挫折知らずの現実的速読トレーニング~」がある。
速読研究会サイトマップ
- 速読研究会トップページ
- やさしい速読動画講座
- 速読とは?初心者のための「理解できる速読」入門ガイド
- 速読トレーニングの方法
- 文字をかたまりで捉えるトレーニング
- 視野を広げるトレーニング
- 視点の移動スピードを速くするトレーニング
- 内音声化のスピードを速くするトレーニング
- 文章構造を素早くつかむトレーニング
- 読解力を鍛えるトレーニング
- 好きな本を読むだけで読むスピードが自然に速くなる、「普段の読書術」👈(現在のページ)
- 速読と仕事・キャリア
- 速読と資格試験・勉強法
- 速読と読書術
- 速読と記憶術
- 速読の科学的根拠と研究
- 速読と語学学習
- 速読と健康・ライフスタイル
- 速読に関するQ&A
- 速読の練習におすすめの本・教材
- 速読講座・速読スクールの比較
- プライバシーポリシー
- 利用規約
- 特定商取引法に基づく標記
- お問い合わせフォーム
- 運営者プロフィール